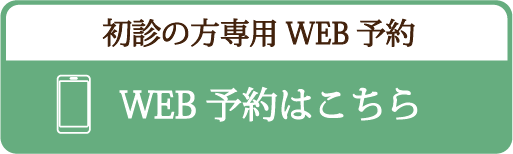
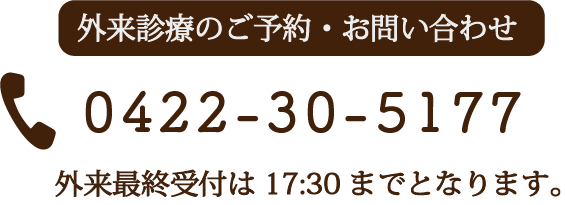
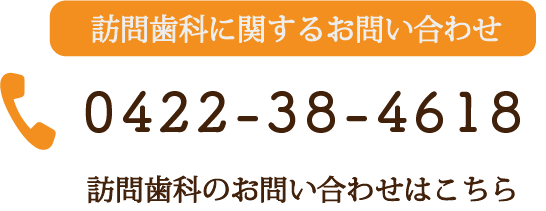
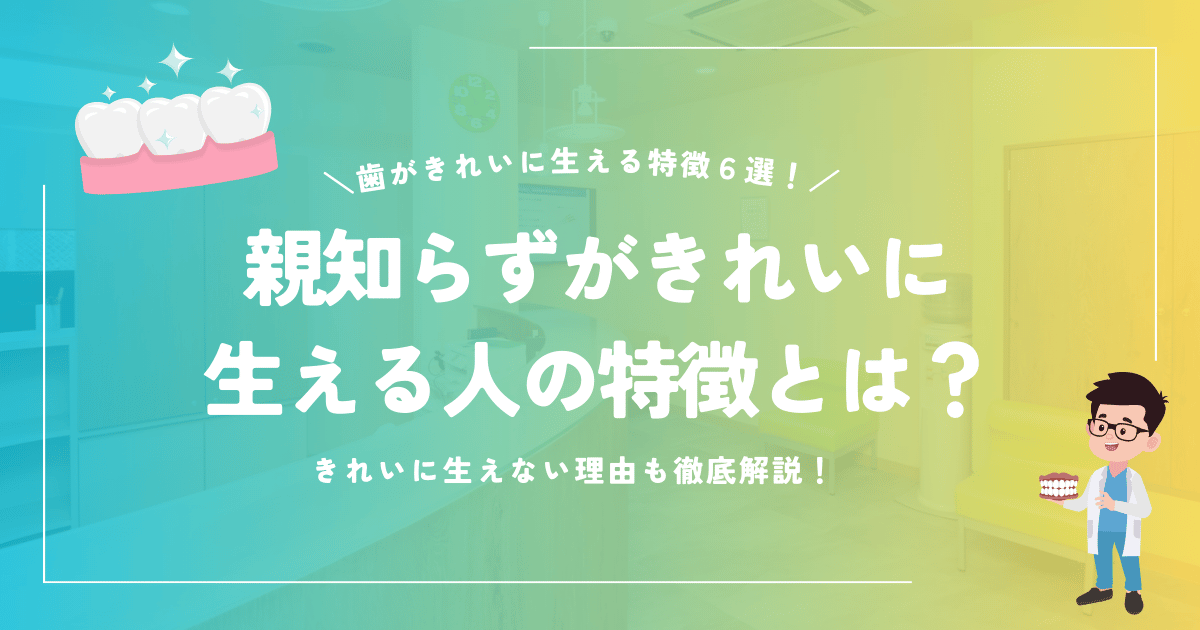
「親知らず=抜くもの」と思っていませんか?実は、きれいに生えてトラブルにならない人もいます。
この記事では、親知らずがきれいに生える人の特徴や、その割合、注意すべきケースまで歯科医師がわかりやすく解説。抜くべきか悩んでいる方や、これから生えてくる方に役立つ情報をお届けします。

歯科医師 星野 真(口腔外科専門医・医学博士)
北海道大学歯学部を卒業後、東京女子医科大学病院で研鑽を積み、口腔外科専門医・医学博士を取得。2011年に武蔵野わかば歯科を開院し、幅広い歯科診療に従事。現在も専門知識を活かし、患者の健康を支えている。

親知らずの生え方には遺伝的傾向があります。両親や兄弟姉妹に親知らずがきれいに生えている人がいる場合、同様の傾向を示すことが多いです。
これは顎の大きさや形状、歯の配列パターンなどが遺伝することに関連しています。一方で、家族全員に親知らずの問題がある場合も、同様に遺伝的要因が影響している可能性が高いと言えます。
親知らずがきれいに生える最も重要な要素の一つは、顎に十分なスペースがあることです。
広い顎を持つ人は、親知らずが正常に萌出するための空間があるため、問題なく生えることが多くあります。
一般的に、顔の横幅が広く、顎の角が発達している人は、親知らずのためのスペースが確保されやすい傾向にあります。現代人は進化の過程で顎が小さくなっており、そのため親知らずのスペース不足が生じやすくなっています。
全体的に歯並びが良い人は、親知らずもきれいに生える傾向があります。前歯から大臼歯まで適切な間隔で配列されていると、親知らずが生えるスペースが確保されやすくなります。
逆に、歯並びが混雑している人や、第一大臼歯・第二大臼歯が後方に傾いている人は、親知らずが正常に生えるスペースが制限されることが多く、問題が生じやすくなります。
親知らずが比較的若い年齢(16〜18歳頃)から生え始める人は、きれいに生える可能性が高いとされています。
これは、若いうちは顎の成長がまだ続いており、親知らずが生えるスペースが確保されやすいためです。一方、20代後半以降に生え始める場合は、すでに顎の成長が完了しているため、スペース不足から問題が生じやすくなります。
口腔内を清潔に保っている人は、親知らずが生える過程でも炎症やトラブルが少ない傾向にあります。特に親知らずが部分的に生えている段階では、歯と歯茎の間に食べ物のカスが溜まりやすく、炎症を起こすリスクがあります。
定期的な歯科検診を受け、適切な口腔ケアを行っている人は、親知らずの周囲炎などの問題が生じにくく、結果的にきれいに生えやすくなります。
幼少期からの食生活も親知らずの生え方に影響します。硬いものをよく噛んで食べる習慣のある人は、顎の骨が十分に発達し、親知らずのためのスペースが確保されやすくなります。
反対に、柔らかい食べ物ばかりを食べて育った人は、顎の発達が不十分になりがちで、親知らずが正常に生えるスペースが不足する傾向があります。また、バランスの良い栄養摂取も歯や顎の健全な発育に重要です。
現代の食生活の変化は、親知らずの問題増加に関連していると考えられます。柔らかい食べ物中心の食生活では咀嚼機能が十分に働かず、顎の発達が抑制されがちです。幼少期から適度に硬いものを噛む習慣をつけることが、将来的な親知らずの問題予防につながる可能性があります。

最も理想的な生え方で、親知らずが歯列の延長線上に垂直に生えている状態です。この場合、歯冠(歯の見える部分)は完全に萌出し、咬合面も適切な位置にあります。正常に生えた親知らずは、他の大臼歯と同様に咀嚼機能を果たすことができます。
また、清掃も比較的容易で、虫歯や歯周病のリスクも低くなります。残念ながら、このようにきれいに生えるケースは全体の約20%程度しかありません。
多くの場合、親知らずは完全に垂直ではなく、斜めに生えてきます。軽度の傾斜であれば機能的な問題は少ないですが、角度が大きくなると隣の歯を圧迫し、歯並びに悪影響を及ぼすことがあります。
また、横向き(水平埋伏)の場合は、隣の歯の根に向かって生えるため、歯根吸収(隣の歯の根が溶ける現象)を引き起こす危険性があります。清掃が難しいため、虫歯や歯周病のリスクも高まります。
親知らずが歯茎や顎の骨の中に完全に埋まっている状態を「完全埋伏」と呼びます。この場合、歯は口腔内から全く見えず、レントゲン検査でのみ確認できます。症状がない場合も多いですが、周囲の組織に圧力をかけて痛みを引き起こしたり、嚢胞(のうほう)と呼ばれる液体の袋を形成したりすることがあります。
完全埋伏の親知らずを抜歯する場合は、歯茎を切開して骨を削る必要があるため、手術の難易度が高くなります。
稀なケースですが、親知らずが通常とは逆の方向(上の親知らずなら上向き、下の親知らずなら下向き)に生えることがあります。これを「逆生埋伏」と呼びます。この状態では親知らずが重要な神経や血管、あるいは副鼻腔などに近接するため、抜歯時の合併症リスクが高まります。
症状がない場合でも、将来的なリスクを考慮して抜歯が推奨されることが多いです。
親知らずの一部だけが歯茎から顔を出し、完全には萌出していない状態を「半埋伏」と呼びます。この状態は最も問題を起こしやすく、歯と歯茎の間に食べ物のカスが溜まりやすいため、「智歯周囲炎(ちししゅういえん)」と呼ばれる炎症を引き起こしやすくなります。
また、対合歯がある場合は、上の歯で下の歯茎を噛んでしまい、痛みの原因となることもあります。清掃が難しいため、虫歯や歯周病のリスクも高まります。
半埋伏状態の親知らずは最も管理が難しく、炎症を繰り返すことが多いです。部分的に生えている場合、食べ物のカスが溜まりやすく、通常の歯ブラシでは十分に清掃できません。この状態が続くと周囲炎を繰り返し、隣接する第二大臼歯にも悪影響を及ぼす可能性があるため、症状がある場合は早めの抜歯を検討すべきでしょう。
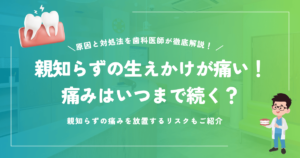
日本人を対象とした研究によると、親知らずが存在する人のうち、問題なく正常に生えるケースは全体の約20〜30%程度とされています。
残りの70〜80%は何らかの問題(埋伏、部分萌出、傾斜など)を抱えています。また、日本人の約25%は少なくとも1本の親知らずが先天的に欠如しているというデータもあります。複数の親知らずが欠如している人も少なくありません。
親知らずが真っ直ぐ正常に生え、かつ噛み合う歯とも適切に噛み合う「理想的な状態」は、全体の約20%程度と言われています。これは5人に1人という割合であり、決して高いとは言えません。多くの人は、親知らずに関して何らかの治療や経過観察が必要な状態にあります。
正常に生える割合は近年減少傾向にあり、これは現代人の顎が小さくなっている進化的傾向と関連していると考えられています。
親知らずの発生率は、世代によって変化しています。過去の世代と比較すると、現代の若い世代では親知らずが先天的に欠如している割合が増加しています。
これは人類の進化的変化とされ、不要となった器官が退化する現象と考えられています。また、親知らずが存在していても、萌出が遅れる傾向も見られ、30代以降に初めて生えてくるケースも増えています。
親知らずの生え方や問題の発生には、男女差も存在します。一般的に女性より男性の方が顎が大きい傾向があるため、男性の方が親知らずがきれいに生える可能性が若干高いとされています。
ただし、この差は個人差に比べれば小さく、女性でも顎のスペースが十分にある人はきれいに生えることがあります。また、親知らずに関する痛みの訴えは女性の方が多いという研究結果もありますが、これは痛みの感受性の違いや受診行動の差も影響していると考えられています。
※参考:小児歯科学雑誌 第57巻(2019年)枡富由佳子ほか「第三大臼歯のエックス線学的形成時期の調査と治療介入時期に関する検討」
親知らずがきれいに生えない原因の一つとして、現代人の顎が小さくなっていることが挙げられます。これは人類の進化の過程で起きた変化で、柔らかい加工食品中心の食生活への移行により、強い咀嚼力が不要になったことが関係しています。
また、脳の発達に伴い頭蓋骨の構造が変化し、顎のスペースが減少したとも考えられています。一方で、歯の大きさはそれほど小さくなっていないため、スペースの不足が生じています。この「顎と歯のミスマッチ」が、親知らずの問題の根本的な原因と言えます。
歯列全体の配置も親知らずの生え方に大きく影響します。前歯や小臼歯が後方に傾いていたり、第二大臼歯(親知らずの一つ手前の歯)が後方に傾斜していると、親知らずが正常に生えるスペースが制限されます。
また、矯正治療を受けた人は、歯を並べるために使用できるスペースが減少し、親知らずのためのスペースが不足することがあります。特に抜歯を伴わない矯正治療では、親知らずの生育スペースが確保されにくくなる傾向があります。
顎の形状や成長パターンも親知らずの生え方に影響します。下顎が小さい「小顎症」の人や、下顎が後方に位置する「下顎後退症」の人は、親知らずが正常に生えるスペースが不足しがちです。
また、顎の成長が不均等に起こると、上下の歯の咬み合わせに問題が生じ、親知らずの正常な萌出を妨げることがあります。顔の形状は遺伝的要因が大きいため、親知らずの生え方にも家族内で類似した傾向が見られることが多いです。
幼少期の栄養状態や咀嚼習慣も、顎の発達と親知らずの生え方に影響します。硬いものをよく噛む習慣は顎の骨を刺激し、発達を促します。
反対に、柔らかい食べ物ばかりを好む、早食いの習慣がある、片側だけで噛む癖があるなどの要因は、顎の発達を不均等にし、親知らずが生えるスペースの確保を難しくします。また、ビタミンDやカルシウムなどの栄養素不足は、顎の骨の形成に悪影響を及ぼす可能性があります。
親知らずの周囲に炎症が生じ、痛みや腫れが繰り返される場合は、抜歯を検討する必要があります。特に半埋伏状態の親知らずは、歯と歯茎の間に食べ物のカスが溜まりやすく、「智歯周囲炎」を引き起こしやすくなります。
この状態が繰り返されると、単なる不快感だけでなく、頬や喉の方向に炎症が広がるリスクもあります。抗生物質での治療は一時的な効果しかなく、根本的な解決には抜歯が必要なケースが多いです。
親知らずが他の歯を押すことで、前歯の歯並びに悪影響を及ぼしている場合は抜歯の適応となります。特に下の前歯が徐々に重なり始めたり、以前は綺麗だった歯並びが乱れ始めたりした場合は、親知らずの圧力が原因である可能性があります。
矯正治療を終えた後に親知らずが生えてきて歯並びが再び乱れるケースもあるため、矯正治療中や治療後の経過観察では親知らずの状態も定期的にチェックすることが重要です。
親知らずが斜めや横向きに生えることで、隣接する第二大臼歯の歯根を圧迫し、「歯根吸収」と呼ばれる状態を引き起こすことがあります。
これは隣の歯の根が溶けてしまう現象で、放置すると隣の健康な歯まで失う可能性があります。また、親知らずと第二大臼歯の間に適切な清掃ができない場合、虫歯のリスクが高まります。隣の歯を保護するためにも、このような状態の親知らずは抜歯を検討すべきです。
親知らずの異常な位置や生え方が、噛み合わせのバランスを崩し、顎関節症の原因となることがあります。顎関節症は、口を開けたり閉じたりする際の痛みやカクカク音、頭痛、肩こりなどの症状を引き起こします。
また、親知らずによる持続的な圧力やストレスが、頭痛や顔面痛の原因となることもあります。こうした症状と親知らずの関連が疑われる場合は、抜歯によって症状が改善する可能性があります。
症状がなくても、将来的にトラブルを起こす可能性が高い親知らずは、予防的に抜歯することがあります。特に若い年齢での抜歯は、骨が柔らかく、根の形成が完全ではないため、手術の難易度が低く、回復も早い傾向があります。
また、年齢を重ねるほど抜歯の合併症リスクが高まるため、将来的に問題を起こす可能性が高い状態(水平埋伏など)であれば、症状がなくても若いうちに抜歯することを歯科医師が推奨することがあります。
親知らずがきれいに生える確率は日本人で約20%程度と低く、多くの場合は何らかの問題を抱えています。抜歯の判断は痛みや炎症の有無、歯並びへの影響、隣接歯への悪影響などを考慮して行われます。
症状がない場合は保存も選択肢ですが、定期的なレントゲン検査による経過観察が重要です。個々の状態に応じた適切な対応で、親知らずによるトラブルを最小限に抑えましょう。
親知らずの有無はレントゲンで確認できますので、気になる方は早めに歯科医院での検査をおすすめします。特に10代後半〜20代のうちに一度確認しておくと、将来のトラブル予防にもつながります。
歯科医師/口腔外科専門医

当院では対応が難しい症例も、CT検査などの最新機器を用いた詳細な診断と安全な手術計画の立案により、確実な治療結果を目指します。
患者様の状態を詳しく診査し、治療方法をご提案させていただきます。
私たちの目標は、患者さん一人一人に、安心・安全で質の高い治療を提供することです。
分からないことや不安なことがありましたら、どんなことでも当院の口腔外科専門医にお気軽にご相談ください。